対話と問題解決力の関係性 │ 「問い」がチームの力を引き出す

あなたのチームには、真面目で優秀なメンバーがいる。
その全員が、黙って資料に目を通し、考え込んでいる。
そんな場面を見たとき、「よし、真剣に取り組んでいるな」と感じたことはないでしょうか?
しかし、もしあなたがリーダーであるなら、その静寂に一度、疑問を投げかけてみてほしいのです。
問題が複雑になり、正解のない問いが増えるいま、一人で考えるだけでは“たどり着けない解”が確かに存在します。
本コラムでは、実際のセミナー現場で起きた印象的な出来事を起点に、「なぜ対話を促すだけで、チームのパフォーマンスが劇的に変わるのか」を、心理学・脳科学的な背景から紐解きます。
これからの時代に求められる、“問題解決力を引き出すリーダーシップ”についてお話しします。
もしあなたが、「チームが自発的に動かない」「問題解決力が伸び悩んでいる」と感じているなら、このコラムにはその突破口があります。
沈黙を破るのは、知識でも経験でもありません。
リーダーである“あなたの問いかけ”と“姿勢”です。
答えを与えるのではなく、考えを引き出す。
そのリーダーシップが、チームを変え、成果を変え、やがて組織の文化さえ変えていくかもしれません。
問題解決力は、リーダーの“問いかけ”と“対話を促す姿勢”によって引き出されるのです。
実話:問題解決セミナーで起きた「静かな違和感」
先日、とある企業で「問題解決セミナー」を実施しました。
その日、私は参加者たちに一つの課題を出しました。
「チームで協力して、ある問題の原因を特定してください」とだけ伝えて。
すると、全てのチームで、誰も何も話さないまま、作業に取り掛かり始めたのです。
メモを取り、資料を読み、黙々と――まるで試験会場のような沈黙が流れていました。
私は試しに、半分のチームにだけ、こう促しました。
「もっとお互いに話をしてみてはどうですか?」
30分後。
明暗は分かれました。
対話を促したチームでは、メンバーが自由に意見を交わし、課題を時間内に解決。
一方、声をかけなかったチームは、黙々と考え続けたものの課題は未完のまま。
そして何より、対話チームには笑顔があり、もう一方のチームには疲労と沈黙が残っていたのです。
なぜ黙って考えるとうまくいかないのか?
一見、黙々と考える姿勢は、「集中している」、「真剣に取り組んでいる」ように見えます。
リーダーとしても、静かな時間を“思考の深まり”と、捉えたくなることはあるでしょう。
ですが、問題解決の現場では、この“沈黙”が、実は思考の停滞やバイアスの固定化を招いていることがあります。
ここからは、「黙って考える」がなぜうまくいかないのか、その背景にある人間の脳や心理の仕組みを解説していきます。
これを知れば、あなた自身のリーダーシップのあり方も、チームとの関わり方も、大きく変わるかもしれません。
ぜひ、先を読み進めてみてください。
認知バイアスと思考の独善性
「黙って深く考える=優秀」という無意識の思い込み。
これは、教育や過去の成功体験からくる、認知バイアスです。
真面目な人ほど陥りやすく、自分の中だけで正解を導こうとします。
ワーキングメモリの限界
人間の脳は、同時に処理できる情報量に限界があります。
対話によって他者の視点が入ると、思考が“立体的”になり、複雑な問題に対する理解が深まります。
優秀な人ほど「協働しない」
「自分でやったほうが早い」と感じる優秀な人ほど、他者との対話を軽視する傾向があります。
ですが、問題解決においては、“自分で抱える”より“他者の視点を活かす”方が、有効です。
心理的安全性の力
「話していい」「出していい」という雰囲気があると、チームの知恵は外に出てきます。
リーダーのちょっとした声かけが、大きな違いを生むのです。
リーダーが意識すべきこと
チームの問題解決力を本当の意味で引き出せるかどうかは、リーダー自身の“関わり方”にかかっています。
ここでご紹介するポイントは、単なるテクニックではありません。
リーダーとしての姿勢、信念、そして日常の小さな言葉や態度に宿る「影響力の使い方」です。
これらを意識することで、あなたはチームに安心をもたらし、対話を生み、沈黙の裏に隠れていた知恵を引き出せるようになります。
しかも、そのプロセスは、メンバーの主体性や成長意欲も引き上げ、結果的に“自走するチーム”へと繋がっていくでしょう。
ぜひ、自分自身のリーダーシップスタイルを点検するつもりで、以下を読み進めてみてください。
1. 対話を促す問いを投げかける
「みんなはどう思う?」
「他にも考えられることは?」
と問いを投げることで、沈黙は破られ、視点は広がります。
2. 正解よりも“納得解”をつくる
唯一の正解を探すのではなく、関係者が納得し、行動できる“現場ベースの解”を共につくることが、リーダーの役割です。
3. チームの沈黙に気づき、「許可」を与える
メンバーが話さないのは、話せないのではなく、“まだ話す許可が出ていない”だけかもしれません。
リーダーが安心感を与えることで、知恵が動き始めます。
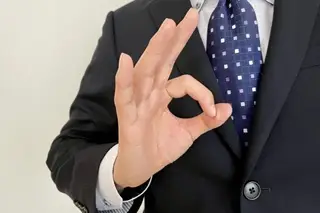
問題解決リーダーのための行動チェックリスト
以下に、会話を促すリーダーが取るべき行動をチェックリスト化してみました。
毎月毎にチェックすることで、あなたの成長も見えてくるはずです。
~チームの“対話”と“発見”を引き出す11の問いかけと行動~
1. 場づくり・空気づくり
・会議やミーティングの冒頭で、「どんな意見でもOK」という安心感を伝えている
・意見が出たとき、「なるほど、それも一つの視点ですね」と受け止める言葉を意識している
・メンバーが話しやすいように、順番を決めず自由発言を許容している
2.思考の可視化・問いかけ
・「なぜそう思ったの?」という“根拠を聞く問い”を活用している
・「他にどんな可能性がある?」という“選択肢を増やす問い”を使っている
・「それって誰の視点?」と、他者視点を促す問いを取り入れている
・ホワイトボードや付箋などで、チームの意見や考えを“見える化”している
3.バイアスへの気づき・視点の交差
・「みんな同じ方向を向いているけど、逆の視点はないか?」と問いかけている
・会話が止まったとき、「あえて違う意見ある人いますか?」と刺激を与えている
・「それって当たり前? 本当にそう?」と前提を疑う発言をしている
4.行動と巻き込み
・「誰と一緒にやるともっと進みそう?」と、協力・巻き込みを促す問いをしている
「黙って考える」は優秀さの証ではなく、思考のワナになることがある
対話によって思考が立体化し、質の高い問題解決が生まれる
リーダーの問いと場づくりが、チームの力を引き出す鍵になる
会話を促す雰囲気作りをはじめてみませんか?


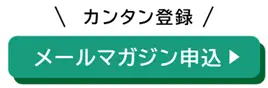 毎週月曜日に「改善ファシリテーション」をテーマとしたコラムを更新、
毎週月曜日に「改善ファシリテーション」をテーマとしたコラムを更新、
火曜日にメールマガジンを配信しております。是非ご登録ください。(ご登録は無料です)

体験セミナーのお申し込みはこちらから
お気軽にお問い合わせください

国内外において、企業内外教育、自己啓発、人材活性化、コストダウン改善のサポートを数多く手がける。「その気にさせるきっかけ」を研究しながら改善ファシリテーションの概念を構築し提唱している。 特に課題解決に必要なコミュニケーション、モチベーション、プレゼンテーション、リーダーシップ、解決行動活性化支援に強く、働く人の喜びを組織の成果につなげるよう活動中。 新5S思考術を用いたコンサルティングやセミナーを行い、企業支援数が190件以上及び年間延べ3,400人を越える人を対象に講演やセミナーの実績を誇る。







