定義を揃えることから始まる、強いチームづくり │ チームビルディングと問題解決をつなぐ視点

「会議で話は出るけど、なぜか噛み合わない」
「チームで決めたはずのことが、なぜかズレて伝わる」
そんな経験、ありませんか?
もしかしたらその原因は、“言葉の定義が揃っていない”ことにあるかもしれません。
このコラムでは、チームビルディングと問題解決の“本当のつながり”を、現場のストーリーとともに紐解きます。
ファシリテーターの視点、認知心理学・行動科学の知見、そしてISOの観点まで交えてお届けする、ちょっと知的で、かつ、すぐに役立つお話です。
およそ10分で読めるボリュームに調整しました。
読み終えたとき、きっとあなたの“言葉の聞き方”が少し変わっているはずです。
「チームビルディングってレクリエーションのことじゃないの?」と思っている方へ
→ 本質は“定義と対話の土台づくり”だという気づきを得られます。
会議や改善活動で「話が噛み合わない」「すれ違いが多い」と感じる方へ
→ その原因が“言葉のズレ”にあるかもしれないことが分かり、対処のヒントが見つかります。
問題解決力を高めたい現場リーダー・管理職の方へ
→ チームの思考を揃える“共通言語”づくりの重要性を、認知心理学と行動科学の視点から理解できます。
ISOや品質マネジメントの実務に携わる方へ
→ 「用語の定義を揃えること」が組織の安定運用のカギである理由が、現場のストーリーとともに腹落ちします。
最後までお付き合いください。
チームビルディングとは「定義を揃える」ことから始まる
「チームビルディング」と聞くと、アクティビティやゲームで楽しみながら仲を深める――というイメージを持つ人も少なくありません。
しかし、本質はもっと地味で、もっと地道な営みです。
それは、「同じ言葉を、同じ意味で使えるようになること」
これができていないと、チーム内で「話し合っているのに噛み合わない」「決めたはずなのにズレが出る」といったストレスが生まれます。
なぜ「具体的な数値」が効果的なのか?
認知心理学・行動科学の視点から
脳は“できるだけ楽をしたい”臓器である
人間の脳は、体重のわずか約2%しかないにもかかわらず、全身の酸素の約20%を消費している、非常にエネルギーを使う臓器です。
だからこそ、脳は常に「できるだけ少ないエネルギーで判断したい」と考えており、曖昧な情報や未定義な言葉には余分な処理を要するため、ストレスや疲労につながりやすいのです。
現場のとある風景
部品の取り付けラインで、作業改善の話し合いをしていたA班。
リーダーが「最近ちょっと作業が遅れてる気がするんだけど、どう思う?」と問いかけると、ある作業者は「まあ、ちょっとバタついてるかもですね」と答えました。
別の作業者は「いや、そんなに変わらないですよ」と返しました。
話し合いは10分以上続いたものの、結局「感覚のすり合わせ」で終わってしまい、対策案は曖昧なまま。
数日後、同じような場面でB班のリーダーは「昨日の出荷タイミング、平均で12秒遅れていたね。どこでロスが出ているか見直そう」と言いました。
するとメンバーは、データをもとに具体的な要因を洗い出し、たった30分で対策がまとまりました。
行動科学:目標は“曖昧”より“数値”が動機を生む
人は曖昧な目標に対しては動きが鈍く、「具体的・測定可能・期限つき」の目標に対しては行動しやすくなるという法則があります(SMART原則)。
会議室でのとあるやりとり
品質改善会議で、リーダーが「もっとミスを減らそう」とチームに伝えました。
しかし、具体的な指示がないため、メンバーの反応は曖昧。
「なるべく頑張ります」「もう少し気をつけます」といった言葉が返ってきただけで、実質的な行動は何も変わりませんでした。
一方、別の日の会議では、リーダーが「今月中にヒューマンエラーを3件以内に抑える。そのために、作業前の声かけを1日2回実施する」と明確に伝えました。
すると、メンバーは対策の行動を具体的に出し合い、進捗を数字で確認しながら取り組むようになりました。
ファシリテーターの現場感から:言葉の“い”に注意を払う
私がチームの会話に耳を傾けているとき、特に注意しているのは「い」で終わる形容詞です。
例)
大きい、小さい
早い、遅い
難しい、わかりにくい
多い、少ない
こういった言葉は、定義が人によってバラつきやすい“主観のかたまり”。
だからこそ、これらの言葉が出てきたときには、必ず「みんな同じ意味で使ってる?」と確認します。
ファシリテーターの現場ストーリー
ある研修で、グループディスカッションをしていたAチームの中で、メンバーが「これ、工程の負担が大きいですよね」と発言しました。
別のメンバーが「でもそれ、そんなに大きくはないと思いますけど」と返し、その後、議論が空回りし始めました。
私はそこで介入し、「“大きい”って、何を基準に言ってる?」と尋ねました。
すると、それぞれが別の基準で「大きい」を使っていたことが分かり、ようやく会話が軌道に乗りました。
ISOでも「定義の一致」が求められている
この「言葉の定義を揃える」というテーマは、品質マネジメントの国際規格である ISO9001 においても非常に重視されています。
実は、ISO9001の運用にあたっては、まずISO9000(品質マネジメントの基本及び用語)という規格文書をベースに理解を揃える必要があります。
例えば、「不適合」「是正処置」「パフォーマンス」「リスク」など、組織内で使う言葉の意味を共通の定義に基づいて使用することが前提とされているのです。
つまり、チーム内で「言葉の定義を揃えること」は、ISO的に言えば「品質の安定と再現性をつくる最も基本的な行動」とも言えます。
定義が曖昧なままのチームに立ちはだかる“5つの壁”
用語の定義を大切にしないチームでは、いろいろな壁が立ち塞がります。
どのような壁が立ち塞がるのか?考えてみましょう。
1.会話迷路:噛み合わない話し合いが長引く
2.価値観の衝突:優先順位が揃わず、ぶつかりやすくなる
3.成果不明のワナ:振り返っても、効果が測れない
4.部分最適の行動:誤解から全体がバラバラに動く
5.ストレスの蓄積:「伝えたのに伝わっていない」ことでお互いに疲弊
最後に伝えたいこと
チーム内で交わされる言葉には、定義をもって行うことが大切です。
その一手間が、対話を深め、ズレを防ぎ、組織を前進させていきます。
用語のすり合わせは地味な作業かもしれませんが、それこそが“考える文化”と“信頼の文化”の土台になるのです。
だからこそ!
「問題が解決しない」
「なんとなく空回りしている」
そんなときは、一度立ち止まって「そもそも、この言葉の定義は揃っているだろうか?」と、見直してみてください。
定義を揃えることが、チームビルディングの土台
「い」で終わる言葉にズレが潜む
曖昧さを数値化すれば、行動が変わる
 定義を揃えることは、チームが進む“地図”を描くこと。
定義を揃えることは、チームが進む“地図”を描くこと。
言葉の共有から、真のチームビルディングが始まります。
最初の一歩として、こんなことから始めてみませんか?
次の会議やミーティングで、出てきた言葉の中から・・・・・
「大きい・小さい・多い・少ない・早い・遅い」などの“い”で終わる形容詞を見つけたら、こう問いかけてみてください。
「それって、何と比べて“多い”と感じてる?」
「“早い”って、具体的にどのくらいを想定してる?」
この一言が、会話を“共有された定義”のあるものへと変え、
チームの思考を揃える第一歩になります。


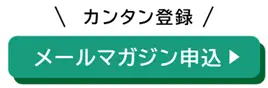 毎週月曜日に「改善ファシリテーション」をテーマとしたコラムを更新、
毎週月曜日に「改善ファシリテーション」をテーマとしたコラムを更新、
火曜日にメールマガジンを配信しております。是非ご登録ください。(ご登録は無料です)

体験セミナーのお申し込みはこちらから
お気軽にお問い合わせください

国内外において、企業内外教育、自己啓発、人材活性化、コストダウン改善のサポートを数多く手がける。「その気にさせるきっかけ」を研究しながら改善ファシリテーションの概念を構築し提唱している。 特に課題解決に必要なコミュニケーション、モチベーション、プレゼンテーション、リーダーシップ、解決行動活性化支援に強く、働く人の喜びを組織の成果につなげるよう活動中。 新5S思考術を用いたコンサルティングやセミナーを行い、企業支援数が190件以上及び年間延べ3,400人を越える人を対象に講演やセミナーの実績を誇る。







